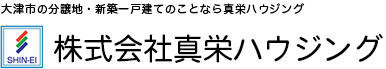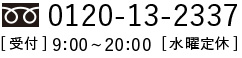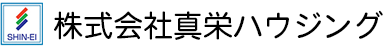滋賀県大津市膳所の旧東海道筋に鎮座する若宮八幡神社は、676年に創建されたと伝わる古社で、天智天皇がこの地を訪れた際、紫雲がたなびき、金色の鳩が大木に舞い降りるという瑞兆が現れたことから、社を建立することとなったのが始まりとされています。
社伝によれば、天武天皇の御代、宇佐八幡の神託を受けてこの地に社殿が造営され、仁徳天皇の御木像が奉納されたという。
創建の翌年には、湖辺上下八町の範囲で殺生が禁じられ、人々がこれを恐れてこの場所を特別の浦すなわち別浦と呼び、後にそれが変じて「別保」と呼ばれるようになり、今もその名残をとどめています。
また、その頃より毎年行われてきた「放生会」は、千三百年を超えて今なお続く伝統行事であり、近年では琵琶湖での蜆流しや人形流しの厄除け神事として斎行されている。
歴史の中でこの社は幾度も災厄に見舞われました。
917年には落雷で全焼し、さらに1184年の木曽義仲の粟津合戦で全焼するが、1202年、源頼朝の上洛の折に再興され、翌年社殿が再建されました。
江戸期には膳所藩の庇護を受け、現存する表門は膳所城の犬走門を移築したものと伝えられています。
また、当社には今も「宮座」の伝統が残っており、元旦や例祭、放生会の日には四季の花を添えた御供が本殿をはじめ摂社・末社に供えられています。
さらに明治十四年に村社、昭和五年には郷社に列せられました。
若宮八幡神社へのアクセスは、電車を利用する場合は、京阪瓦ヶ浜駅で降りて徒歩で約3分、自動車を利用する場合は、名神高速道路大津ICから約10分です。
びわ湖や比叡山などの豊かな自然に囲まれた土地で新築一戸建て・分譲地をお探しの方は、お気軽に大津市の真栄ハウジングにご相談ください。