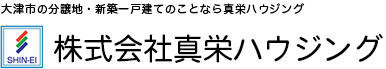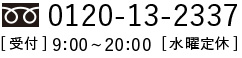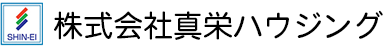滋賀県大津市、京阪電鉄石山坂本線の錦駅から北へ進み、滋賀大学附属小学校の東側に鎮座するのが石坐神社です。
石坐神社の創建年代は明らかではありませんが、古代から続く由緒ある神社であり、地元住民の信仰を集めてきました。
祭神は彦坐王をはじめ、天智天皇、伊賀采女宅子媛命、その子・弘文天皇(大友皇子)、豊玉比古命、海津見神などで、彦坐王、天智天皇、伊賀采女宅子媛命、弘文天皇の神像は平安時代から鎌倉時代にかけての作で、重要文化財に指定されています。
社伝によれば、この神社の起源は近江国府の初代国造・治田連が、その祖先である彦坐王を茶臼山に葬り、背後の御霊殿山を神体山として祀ったこととされます。
彦坐王の詳細な事績は定かでないものの、その子孫である治田連一族が湖南地域での農業や漁業、水利事業の発展に大きく貢献したことで、彦坐王は地域開発の祖として敬われるようになりました。
その後、天智天皇の時代になると、深刻な旱魃が発生し、湖水から御霊殿山へ飛ぶ神秘的な竜燈が目撃されました。
この現象により派遣された勅使の前で竜燈が姿を変え、「われは海津見神の幸魂である」と告げて雨をもたらしたと伝えられています。
この霊験あらたかな神として、海津見神も御霊殿山に祀られることとなりました。
壬申の乱以降は、近江朝の神霊を祀ることは一乗院滋賀寺に限られていましたが、持統天皇の時代に滋賀寺の僧・尊良法師が神殿を建立し、ひそかに近江朝の神霊を奉斎すると、その後石坐神社は「八大龍王宮」とも称されるようになりました。
石坐神社へのアクセスは、電車を利用する場合は、京阪石山坂本線錦駅を降りて徒歩で約8分、自動車を利用する場合は、名神高速道路大津ICから約15分です。
びわ湖や比叡山などの豊かな自然に囲まれた土地で新築一戸建て・分譲地をお探しの方は、お気軽に大津市の真栄ハウジングにご相談ください。